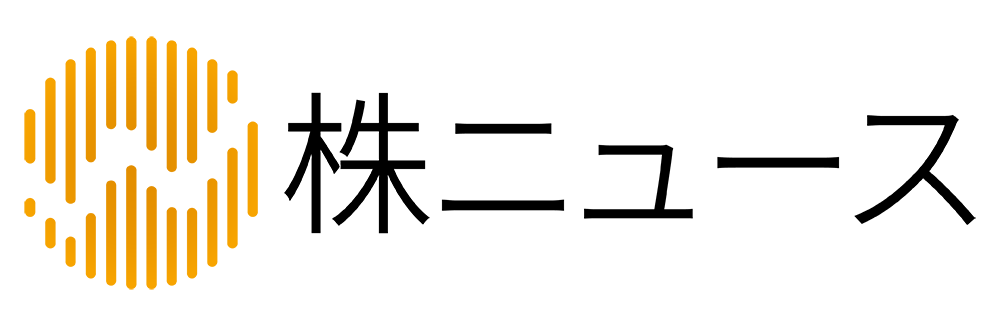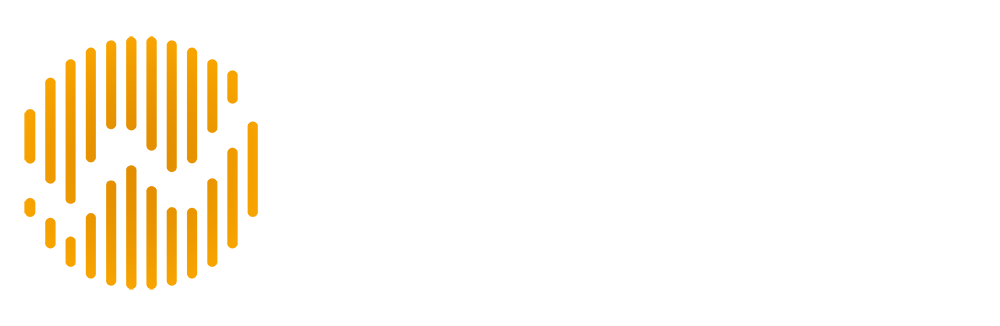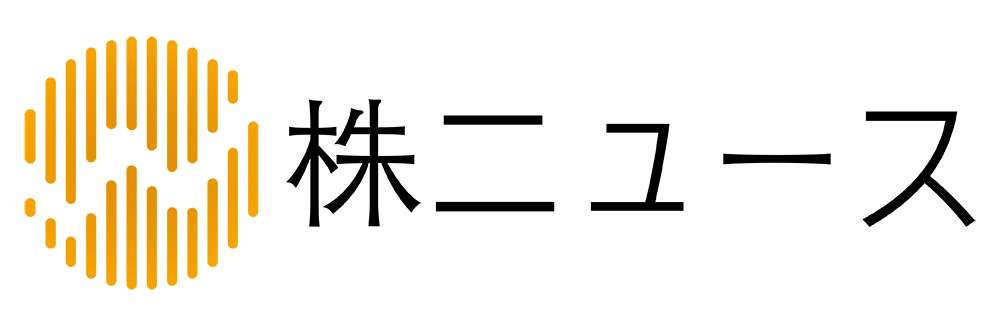大型水槽の導入でコストを劇的に削減
水産研究・教育機構とヤンマーホールディングスは7月8日、ウナギの稚魚を効率よく育成できる新型の大型水槽を共同開発したと明らかにした。今回の技術革新により、1尾あたり約4万円かかっていた稚魚の生産コストが、およそ1800円まで低下した。この削減率は20分の1以上に相当し、長年の課題だった完全養殖の商業化に向けた重要な一歩とされている。
新開発の水槽構造と素材の特徴が判明
今回の水槽は、飼育作業の効率性やウナギ幼体の成長に最適な環境を重視して設計された。素材には安価かつ大量生産が可能な繊維強化プラスチックを採用。水槽の形状も従来型と異なり、ウナギの移し替え作業や成長に最適化されている。これにより、作業負担の軽減と生育率の向上が同時に実現された。
大量育成による実証成果が報告される
新水槽を用いた実証実験では、1台の設備で1000尾の稚魚を人工的に育てることに成功した。この大量育成とともに、給餌や水質管理といった飼育システムの見直しも進められ、生産コストのさらなる低下に寄与している。量産体制における技術的な課題が着実に解消されつつあることを示す成果といえる。
商業化の壁を突破する新たな契機に
ウナギの完全養殖技術は理論上確立していたが、稚魚の育成にかかるコストの高さが最大の障害となっていた。今回の水槽開発により、その障害が現実的に解消される可能性が出てきた。今後はさらなる設備の最適化や流通面での整備が課題となるが、商業生産への道が大きく開かれたことは間違いない。
国際規制への対応と資源保護の観点が影響
ウナギ資源の減少を受け、欧州連合はニホンウナギを含むウナギ全種について、国際取引の規制強化を提案している。日本は食用ウナギの多くを中国などから輸入しており、価格高騰や供給不安の懸念がある。この状況を受け、日本政府は資源保護の一環として完全養殖の推進に力を入れており、今回の技術進展はその方針とも合致している。