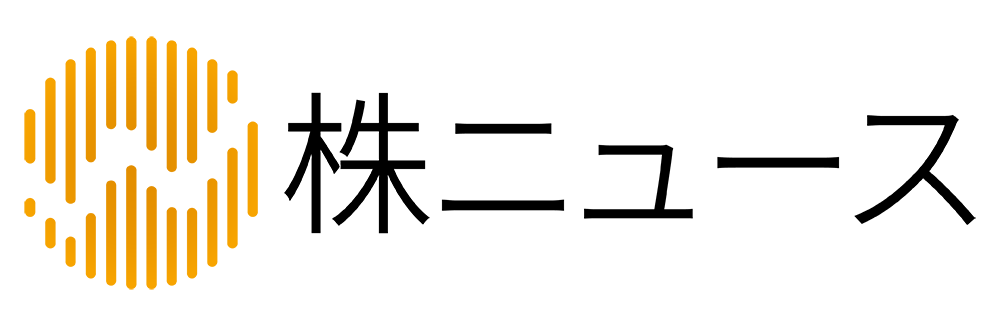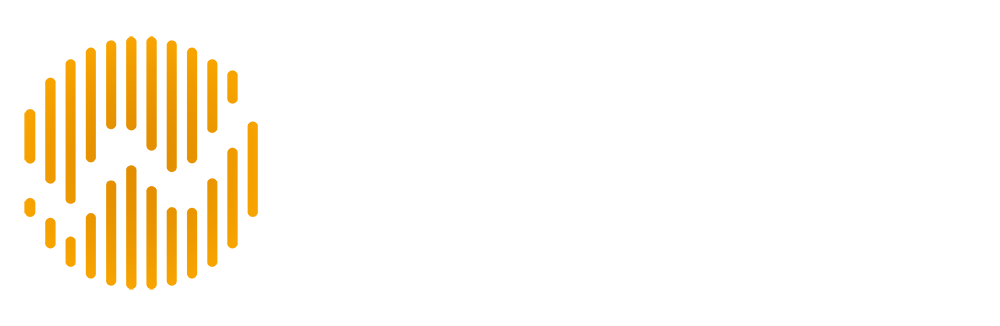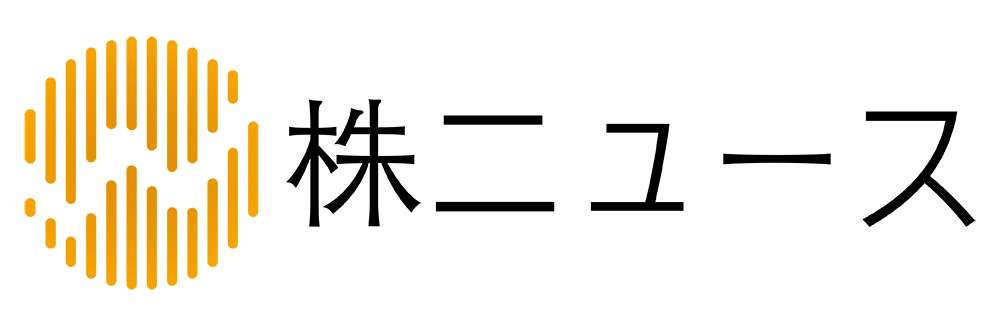求人倍率の下落、全国平均で1.24倍に
2025年2月の有効求人倍率は全国平均で1.24倍となり、前月から0.02ポイント下落した。これは2024年8月以来、6か月ぶりの下落となる。厚生労働省は、企業における人手不足が依然として深刻である一方、物価やエネルギーコストの上昇が新規求人の抑制に影響していると分析している。
地域別では福井県が最高水準、大阪府が最低
都道府県別の有効求人倍率を就業地ごとに見ると、最も高かったのは福井県の1.85倍であった。続いて山口県(1.69倍)、香川県(1.66倍)と続く。一方、最も低かったのは大阪府の1.04倍で、北海道(1.06倍)、福岡県と沖縄県(いずれも1.08倍)も低水準だった。地域ごとの経済環境や業種構成の違いが、求人需要の格差を生んでいる。
主要産業で求人減、宿泊・飲食業は大幅な落ち込み
新規求人数を産業別に見ると、主要な11業種すべてで前年同月比の減少が見られた。とりわけ落ち込みが大きかったのは「宿泊業、飲食サービス業」で前年比17.6%減。「生活関連サービス業、娯楽業」が10.5%減、「建設業」が9.1%減、「製造業」が6.5%減となっている。インフレの進行や光熱費の上昇により、企業が新たな雇用を控えている実態が明らかとなった。
建設・製造業でも求人抑制、労働需給のギャップ続く
建設業や製造業といった基幹産業でも、新規求人の減少が顕著である。厚生労働省は「人手不足が続く中でも、コスト負担増が企業の採用意欲を下げている」としており、今後の雇用動向について引き続き注視が必要だとしている。特に、労働市場における需給ギャップが続けば、景気回復にも影響を及ぼす可能性がある。
景気回復の足取りに影、雇用環境の不透明感強まる
今回の有効求人倍率の下落は、企業の採用抑制が広がりつつあることを示しており、景気回復の勢いにブレーキがかかる可能性もある。政府は、雇用支援策や企業向け補助金の活用を含め、企業活動と雇用の維持を両立させる政策の実行が求められる。今後の物価動向やエネルギー価格の推移によって、企業の採用戦略が左右される局面が続くとみられる。