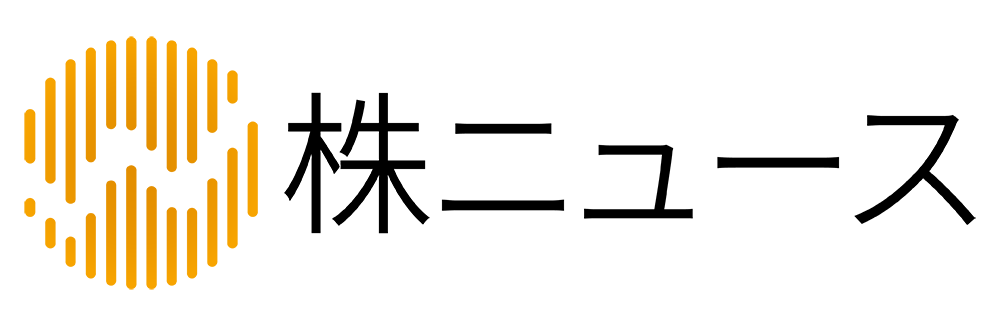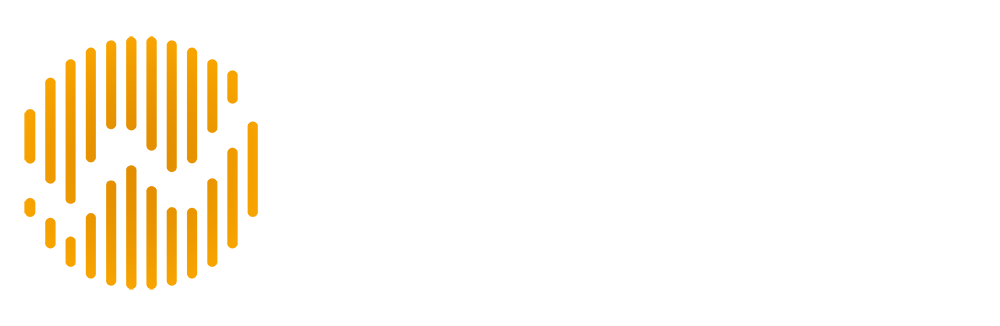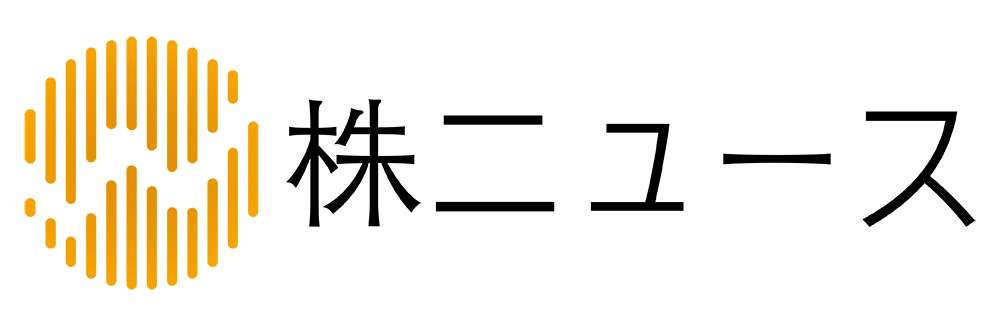6月時点での作付け意向が大幅に拡大
農林水産省が集計した2025年産の主食用米の作付け意向は、6月末時点で前年より56万トン多い735万トンに達する見込みとなった。4月時点からもさらに16万トン増えており、作付面積も前年比で10.4万ヘクタール拡大して136.3万ヘクタールに到達する見通し。これは2004年以降の最多増加幅となる。
高騰する価格が作付転換を促進
ここ数年、主食用米の流通量が不足し、価格の上昇が続いていた。22〜23年産における計65万トンの供給不足がその要因とされている。高値傾向を受け、農家の多くが飼料用・加工用から主食用へ生産の重点を移し、今回の増加をもたらした。農水省の幹部は「農業現場には依然として拡大の余地がある」と話す。
農相が農家の努力を評価 支援策に言及
小泉進次郎農相は会見で「農家の皆さまの努力に感謝する」と述べ、価格上昇への対応が現場で進んでいることを評価した。また、主食用米への転換の拡大により、酒米の供給に不安の声が出ていることも紹介し、新たな支援策の創設方針を明らかにした。
政府の対応 市場流通の促進へ転換
民間市場での米の流通量を確保するため、政府は備蓄米の買い入れを一時停止すると決定した。これにより需給の逼迫緩和を図る。7月初めの関係閣僚会議では、石破首相が主食用米の増産に向けた政府の方針を改めて表明した。
酒米生産への影響と対策の必要性
主食用米への偏重が進めば、他用途の作付け縮小が懸念される。特に、日本酒業界では酒造用米(酒米)の不足が問題視されている。農相は26年度予算への支援策計上を指示しており、今後の対策が注目される。