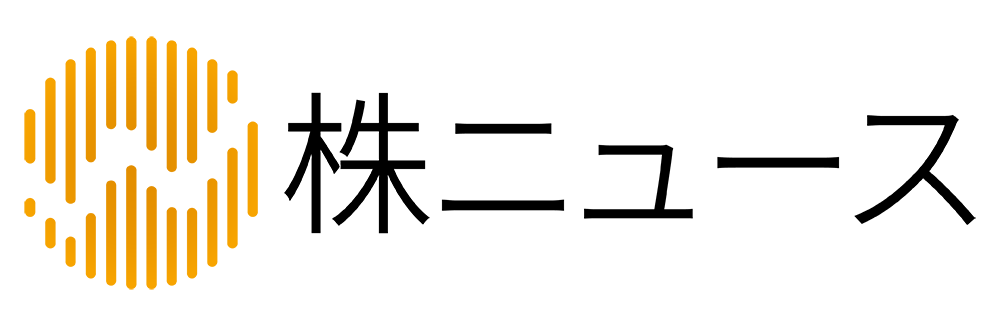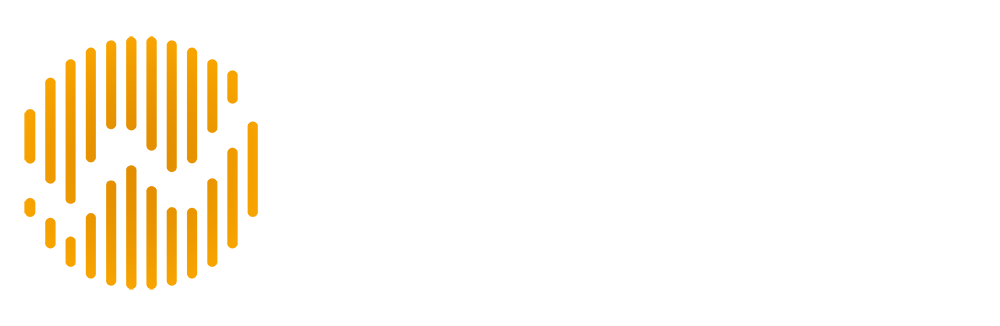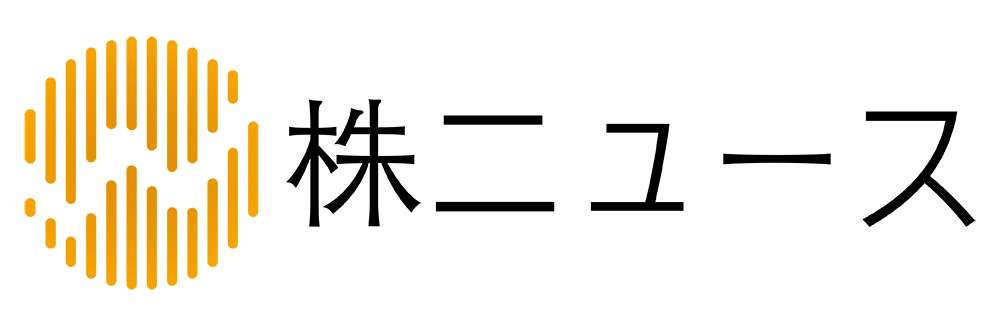農水相が制度見直しを表明 70年近い歴史に幕
6月16日、小泉進次郎農林水産相は、1956年から続いてきた「作況指数」の公表を2025年産を最後に中止すると明言した。実際の生産現場との間に乖離があるとの批判を受け、制度の見直しに至った。
目次
平年との比較に限界 現場感覚と指標のズレ
作況指数はその年のコメの収量を30年平均の「平年収量」と比べて算出され、5段階の評価で示されてきた。だが、昨年の指数が101と「平年並み」とされたにもかかわらず、コメ不足感と価格高騰が続いたことから、指標と実態のズレが顕著となった。
今後は前年との比較に移行 収量調査は継続
農水省は、従来の作況指数に代わり、前年との比較を基本とした作柄評価に移行する。これにより、農家や関係者がより現実的な判断をしやすくなることが期待されている。なお、全国約8,000区画を対象とする収量サンプル調査は今後も継続される。
測定基準も見直し デジタル技術の導入を検討
農水省は、主食用玄米のふるい分け基準として一般的な1.7ミリから、実情に即した1.8〜1.9ミリへの移行を検討している。また、衛星からの観測や大規模農家から得る収穫データの活用によって、統計の質を高める方針だ。
政策判断の基盤強化へ 農業の現場重視姿勢強調
小泉氏は会見で「精度の高い情報を基に、農業政策の基盤を刷新したい」と述べた。これまでの画一的な指標ではなく、現場に即した柔軟なデータ活用が求められる中で、制度の見直しは農業行政の転換点となる可能性がある。