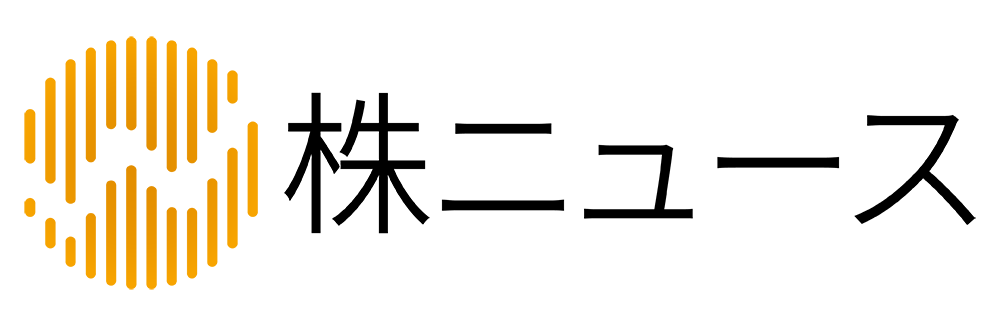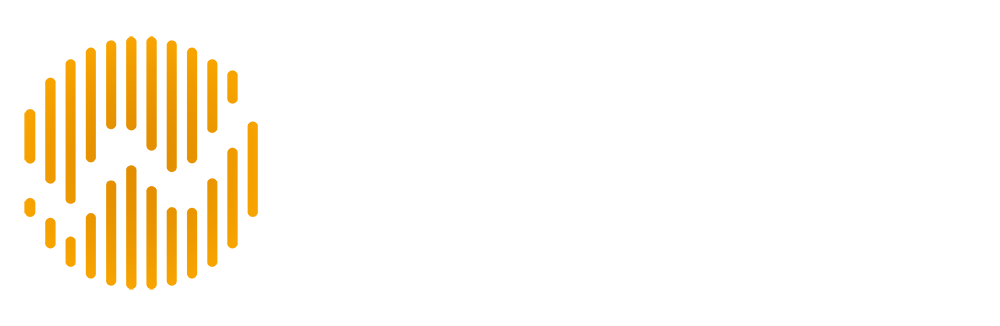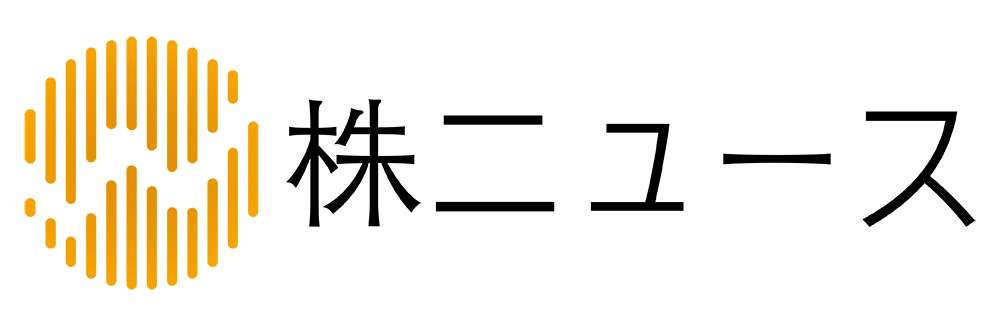国内品種の特徴と輸入依存の現状
日本の食卓に欠かせない大豆は、豆腐や納豆など幅広く利用される。国産品種は粒が大きく、形も整っており、タンパク質を多く含む点が強みとされる。しかし、収量は10アールあたり約170キロにとどまり、米国やブラジル産の半分程度にすぎない。このため、日本は食品用大豆の約8割を輸入に依存している。
農研機構が遺伝子解析を発表
農業・食品産業技術総合研究機構は18日、国内外462品種の遺伝子を網羅的に解析した結果、国産大豆に共通して粒を大きくする遺伝子配列を特定したと公表した。兵庫県の「丹波」や山形県の「だだちゃ豆」といった伝統的品種に、この遺伝子が確認されたことは大きな成果とされる。
米国品種との交配で収量増を目指す
米国産大豆は小粒ながら収量が多いという特性を持つ。農研機構は既に米国品種と交配させた「そらひびき」を開発してきたが、品質が安定して国産の特徴を保持するには課題が残っていた。今回の発見によって、国産の品質と米国品種の収量性を両立させる取り組みが本格化する見通しである。
品質維持と収量増加の両立が現実味
従来の交配では収量は増加したものの、国産特有の品質が失われることが懸念されていた。今回の遺伝子解析は、品質を維持しながら収量を拡大できる科学的根拠を提供するものであり、従来の限界を超える可能性を示している。
自給率向上への期待
日本は大豆の安定供給を海外に依存している状況にあり、国内生産の強化は大きな課題とされてきた。今回の研究成果は、自給率の改善に直結する品種開発に向けた基盤を築いたといえる。農研機構は今後も交配を重ね、収量と品質を兼ね備えた革新的品種の育成を進める方針を示している。